
頭痛はいくつかの種類に分かれており、タイプによって対策も違います。
日本人の多くは首・肩の筋肉の緊張で痛みが起こる「緊張型頭痛」といわれています。この緊張型頭痛と同じく、慢性的におきる頭痛(慢性頭痛)の一つに「片頭痛(偏頭痛)」があります。
ここでは突然、片頭痛が始まったときの対処法と、日常的にできる予防法もご紹介していますので、ぜひ参考にしてくださいね。
片頭痛とはどんな頭痛?
片頭痛とは、こめかみ付近でズキズキと脈を打つような、強い痛みが特徴の頭痛です。
名前にあるように、頭の左右どちらか片側に発生することもありますが、頭全体が痛くなる場合もあります。
発作的に現れた痛みは、数時間から2~3日続くこともあり、その間は色、音、においに敏感なりやすいため、人によっては吐き気をともなうこともあるようです。
片頭痛の代表的な症状をまとめると、次のような特徴がみられます。
- 頭がズキズキと脈を打つように痛い
- 頭痛が発生する前に、目の前がチカチカしたり周りが見えにくくなったりする
- 1か月に1~2回ほど頭痛が起きる
- 体を動かすことで頭の位置が変わると痛みがひどくなる
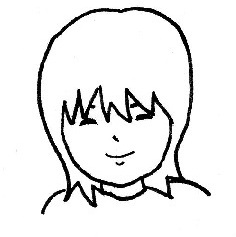
片頭痛は慢性頭痛の中で緊張型頭痛の次に多い頭痛のタイプであり、特に20~40代の女性が発生しやすいといわれています。
片頭痛はなぜ起きるの?
片頭痛がなぜ起きるのか、明らかな原因は見つかっていません。
しかし、痛みのもとは頭蓋骨の中を通る血管が拡張して炎症を起こしているためといわれています。
そして、その要因として神経伝達物質のセロトニンが関わっていると見られており、セロトニンの分泌には女性ホルモンのエストロゲンが影響することから、男性に比べて女性の方が片頭痛になりやすいのではないかと考えられています。
偏頭痛になりやすい人の特徴
体質の他に片頭痛になりやすい人の特徴として、努力家、完璧主義、神経質な性格も影響しているとされ、精神的・肉体的ストレスや食生活なども痛みを発生する要因になる場合があるようです。
片頭痛が起きたときの対処法

片頭痛が起きたときは、静かな部屋で痛む部分を冷やしながら、できれば横になって休むことをおすすめします。
仕事中など、横になって休めないときは、こめかみを押さえて血液の流れを阻害し、座ったままで体をできるだけ動かせないようにしましょう。
片頭痛の症状のピークは、約1~2時間といわれているので、この間は無理をしないようにしてくださいね。
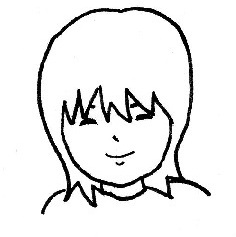
反対に頭痛が起きているとき、絶対やってはいけないことは、入浴、運動、マッサージなど、血管を拡張してしまう行為です。×
片頭痛のときカフェインを飲む場合の注意点
片頭痛が起きているとき、コーヒー、緑茶、ウーロン茶、紅茶など、カフェインを含む飲み物をのむと、症状がやわらぐといわれます。
これは、カフェインに血管を収縮する作用があるため、片頭痛の症状を鎮めてくれると考えられています。
ただし、片頭痛にいいからといってカフェインを飲み過ぎると、反対にカフェインの作用で頭痛が起きてしまうこともあるので、くれぐれも注意してください。
日常生活でできる片頭痛の予防方法

片頭痛は体質、性格、生活習慣など、さまざまな要因がきっかけとなり発生してしまいます。
片頭痛を誘発するものは一人ひとり違うため、まずは自分がどのような条件で片頭痛が起きるのか、知ることから予防対策を始めましょう。
例えば、色、音、ストレス、体調、食事、乗り物、服用した薬など、片頭痛が起きたときの条件をメモに残しておいて、できるだけ片頭痛が起こりやすい状況を避けることが予防につながります。
食事の面では、血管の拡張を促すポリフェノールを含む食材を食べ過ぎると、頭痛が起きることもあるため注意をしてください。
長引く片頭痛は医師に相談を
長引く片頭痛は我慢せずに、病院で適切な治療を受けることをおすすめします。
最近では、頭痛が起きる前に服用する予防薬を使った治療法が注目されています。
まとめ
片頭痛は強い痛みが特徴ですが、症状が起きてもほとんどの人が病院へ行かず、対処しているといわれています。
しかし、片頭痛は突発的に発生することがあるため、症状がひどくなると仕事や家事が手につかず、日常生活への影響も避けられなくなってしまいます。
片頭痛対策には、痛みを起こす条件をできるだけ遠ざけるとともに、頭痛が起きた場合は静かに休むようにしてください。
そして、セルフケアで改善しないときは、早めに病院を受診するようにしましょう。
| 記事の内容は執筆当時のものになります。また、記事の内容には個人差があるためご了承くださいませ。 |

